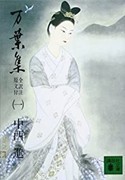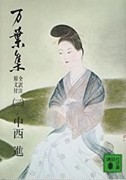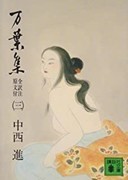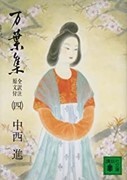国は一定区域をなす土地を表わす言葉で,歴史的には,さまざまの範囲を呼ぶのに用いられた。例えば古く『後漢書』に,1世紀の倭国に百余国があったと書かれている。大化改新を経て国郡制が成立。郡の上に国司の治める新たな国を置くこととし,日本全国は8世紀初めに五畿七道に大別され58国3島,10世紀初めの《延喜式》では66国2島とされた。現在では,国とは土地,人民,政府をもつ国家のこと(百科事典)。
高光るわが日の皇子の万代(よろづよ)に国知らさまし島の宮はも
万葉集・日並皇子宮の舎人
*草壁皇子は現在の島庄にあった島の宮という離宮に住んでいた。この歌では皇子亡き後、島の宮に出仕した舎人が、草壁皇子が天皇となりこの島の宮から永遠に国を治めてほしかったのにと嘆いている。「高く光るわが日の皇子が永遠に国を治めてほしかったこの島の宮よ。」
高光る: 「日」にかかる枕詞。
いふ言(こと)の恐(かしこ)き国そ紅(くれなゐ)の色にな出でそ思ひ死ぬとも
万葉集・坂上郎女
*「人の言葉の恐ろしい国です。紅の色のように表には出さないでくださいね。秘めた思いの苦しさに死んでしまいそうでも…」 人の噂になることの恐ろしさを詠んだもの。
君を待つ松浦(まつら)の浦のをとめらは常世(とこよ)の国の海人をとめかも
万葉集・吉田 宜
*「あなたを待つという松浦川の浦の少女たちは、きっと神仙の国の天女ですね。」
草も木もわが大君の国なればいづくか鬼のすみかなるべき
太平記・紀 朝雄
*「草も木も、この世に生を享けるものはすべて天皇の治に従う。鬼といえども、天皇に背いてこの国に住むことはできない。」
世々たえずつぎて久しくさかえなむ豊蘆原の国やすくして
玉葉集・伏見院
あきらけく岩戸をいでし朝(あした)より天照神の国ぞさかゆる
新続古今集・足利尊氏
国を思ひ寝られざる夜の霜の色月さす窓に見る剣かな
橘 曙覧
*橘 曙覧: 江戸時代後期の国学者,歌人。国粋思想をとなえ,万葉調の歌をよんだ。